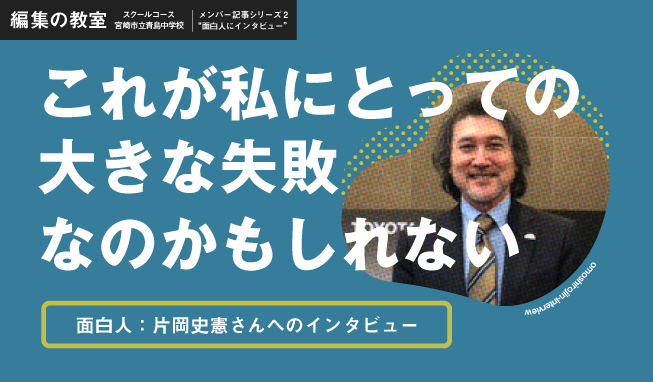「便利」と「カルチャー」の共存。[D-Stadium編集部・企業インタビュー:株式会社セブン&アイ・ホールディングス]
コンビニエンスストア、スーパーストア、百貨店、専門店、金融サービスなど幅広い業態を擁するセブン&アイ・ホールディングス。子会社であるコンビニエンスストアのセブン‐イレブン・ジャパンの店舗数は、全国で2万店を越え、2007年からスタートしたプライベートブランド「セブンプレミアム」は、今や4,000以上のアイテムを揃えている。
2009年、セブン‐イレブン・ジャパンは、「『近くて便利』なお店を目指す」というコンセプトを掲げ、常に新しい便利さを提供することに取り組んできたという。今やその存在に「便利だけではない何か」があるのではないか?セブンプレミアム開発戦略部で企画マーケティングを担当している金子美緒さんにお話しを伺った。

「便利」という選択肢で寄り添えたら。
以前、知り合いの不動産屋さんから聞いたことがある。お客さんの土地探しの条件の一つに出てきたのは「セブン‐イレブンが近くにあること」。当時、いわゆる自然派でコンビニと縁遠かった私は、「便利」がそんなに必要なんだな、くらいにしか思っていなかった。あれから1年経ち、外で働くようになった私はオフィスの近くにあるセブン‐イレブンに足繁く通うことになる。そして今やどこに行ってもセブン‐イレブンを探している自分に気がつく。どうしてだろう?まだ明確な理由は見つからない。ただ、土地探しの条件が「コンビニ」ではなく「セブン‐イレブン」だったことは少し理解できる。
「便利」だけではないから?という自分の中に生まれた問いを懐にしまい、金子さんにとって「便利」とは?そこからお話しを伺った。
「うーん、便利って色々ありますよね。さっと買えるとか、駅が近いとか。私は元々、すごい田舎に住んでいて、駅も学校も遠い生活だったので、一人暮らしをした時に駅近に住んだんですよ。すごい便利だなあとは思ったんですけど、駅から5分でも20分でもどっちでもいいなと思ったんですよね」
ジャンクフードも手作り料理も好き。田舎も都心のホテルも好き。仕事のオンとオフも区切らない、という金子さん。
「欲張りなだけかもしれませんが、どっちの良さもある。どちらがいい、というこだわりはなくて、感覚的に自分がいいと思ったら、それがいい」
絶対的価値は余白がない。そんな息苦しさとかけ離れた返答は、どこか心地が良い。調子に乗って「便利すぎて料理しなくなるんじゃないか」という「便利」が秘めている怖さを投げかけてみた。
「個人的な意見ですけど、いくら便利でも、みんな料理しなくなるということはないと思うんですよね。料理する楽しみってあるだろうから。ただ、例えば、今日の夕飯、子供がいないから買って食べよう、とか、お昼さっと食べたいとか、人それぞれのシーンがある。そういうシーンで「便利」と思ってもらえて、家族でもっと話せる時間が増えたとか、自分の時間が作れるとか、子供と遊ぶ時間ができたとか、そんなふうに寄り添えるものだったらいいんだろうなって」
金のハンバーグをリニューアルし続ける理由。
実は私もここ数ヶ月、お酒を呑んだ後のシメはセブンプレミアムの坦々麺と決めている。まさにそうやって人それぞれのシーンに登場するから、本人とのストーリーが生まれているのかもしれない。
「もしかして、なんですけど、そうやってお客様とのストーリーが生まれるのは、うちは商品が軸だからかもしれない、って思いました。とにかく商品を大事にする会社なんです。どれだけお客様に喜ばれる商品を作るか、って一品一品を大切にしていて。『7プレミアムゴールド 金の直火焼ハンバーグ』(以下、金のハンバーグ)なんてリニューアルして10代目なんですよ(笑)」。
「社内のみんなが話す時はいつも商品が中心」。そごう・西武の百貨店から出向で現職に携わる金子さんにとって、その姿勢は「自分たちで物を作る」という創業からのDNAを感じるという。
「いわゆるプライベートブランドの安かろう悪かろうのイメージではなく、安さを追わないで質を追う、プライドブランドという言葉を掲げてますが、本当にそういう話を社内で何百回も聞いているんじゃないかな。でもその精神が脈々と続いているのは私はすごいと思っています」。

日常のシーンの積み重ねが紡ぎ出すもの。
「金のハンバーグを子供がまた食べたいっていうから買いに来ました、というお客様がいらっしゃったのですが、家族で食べて美味しいねって言ってくれてたのかな、って勝手に想像したりして。商品としてそういうシーンを生み出せるのはいいなって思います。
そしてやっぱりそういうシーンに登場するのは、根底に『美味しい』があるんだと思います。『美味しい』は主観的な言葉だからあんまり使うのは好きじゃないんですけどね。でも手に取ってもらえるだけでも奇跡なんだろうなと思っているので、手に取ってくれた人に喜んでもらう、そこはみんな全神経を注いでやってるなと思います」
日常のシーンの積み重ねが、カルチャーを作り上げていく、ということなのかもしれない。金子さんご自身にも食を通して思い出すシーンはあるのだろうか?
「何十年も前ですけど、うちの祖母がセブン‐イレブンのラムレーズンのアイスが好きで。いつも祖母に買ってきてって言われて、当時はお店でディッシュアップするスタイルだったので、お店でアイスをカップに入れてセブン‐イレブンの蓋をつけて持って帰ってました。そのシーンがね、ふとした時に浮かぶんですよ。誰かに祖母の話をした時とかに」
愛されるのを待ってるだけじゃ愛されない。

良い品質のものを作る。でもそれはただ売れればいい、というよりは「なんか好き」って言われたい、と金子さんは言う。
「安全・安心とか、美味しいとかは言わずもがななんですけど、愛される存在になれたらいいなと思っています」。でも人間の場合でも、愛して欲しいって言うだけじゃ誰も愛してくれないですよね、と切り返すとこんな言葉が返ってきた。
「そうなんです。だから愛されるのを待ってるんじゃなくて、自分たちから歩み寄るのは必要なんだろうと思ってて。社内のチームでも『圧倒的生活者視点をもつ』ということを忘れないようにしようと。どうしても我々は作り手なので、作り手視点でプロダクトアウト的な発想になりがちなので。こんな機能もつけました、便利でしょ?って言っても、お客様は全然そんなものを求めてなかったりしますよね。ハイスペックが必ずしも良いわけでもない。お客様が何を求めているのかを知ろうとすることが必要なんだと思います」
現在、健康食品の開発を担当しているという金子さん。こんな苦悩をちらりと覗かせた。
「私は基本的にジャンキーな食べ物も好きだけど、でも痩せたいって思ったりもする。健康生活を送りたい人もきっと同じで、たまにはアイスも食べたいだろうな、って思うんです。”食”って、単なる食糧じゃない、癒しや楽しさの価値があるはずだから、それを健康食品とひとくくりにしてしまうのはなんか違うのかなあって。そういうお客様の視点に立った提案をしたいのですが、これが難しくて、、、まだまだ模索中です」
作り手側の押し付けになってはいないか?と自分に問いかけながら、日々過ごしているのであろうその姿は、その先に相手があるからこそ。私は商品を通して、愛されてるんだなあ。そう感じてしまった。
だからこそ、いつかあの坦々麺も私にとってのカルチャーになるのかもしれない。金子さんにとってのおばあちゃんとラムレーズンのように。
中学生の取材を受けて
変化に対応できていなかった自分を見つめ直すきっかけにも。
インタビュー中、学生のみなさんが自分たちの日常もリアルに語ってくれたのが印象的でした。商品に対して誠実さを求めていたりとか、自分の中学生時代とは考え方が全然違ってきているのだなと実感。当社には「変化への対応と基本の徹底」という長年変わらないスローガンがあるのですが、自分は変化に対応できていなかったんだなと改めて考えさせられたし、個人としても企業としてもいろんな人とお話しすることの大切さを学ばせてもらいました。
■D-Stadium「編集の教室」に参加の中学生が書いた企業インタビュー記事は、こちらから。